・・・「草レースやろうぜ!」MOUNTAIN CIRCUS 2 TANZAWA(その1)からの続き。
「大きな問題点」
まず関東は都心から山が遠く、必ずしもアクセスの良い場所に良いロケーションがあるわけではないということ。そして、メンバーの住まいもバラバラでチームも違うし、こういったチームの団結力が問われるイベントがやりにくい環境にあった。
なので、先ずはチームの垣根を取っ払って、両チームメンバーをごちゃ混ぜにしてコース班、会計班、医療班、会場、前夜祭班、賞品班、エイド班、計測班、交通班、撮影班、WEB班など各セクションにリーダーを立てて小さなプロジェクトに分けてそれぞれが独自に動けるようにした。そして、facebookのグループ機能を活用して情報交換をして離れて住んでいる欠点を解消した。そして毎月一回、岩本町のOne drop cafeで定例会議を開いて、各班の懸案事項を持ち寄ってその場で決定していくという何だか会社みたいな事をしていた。

MC2定例会議の風景@One drop cafe
そして、もう一つの肝心のコースの問題。地理的な問題は場数を踏むしかない。個人的な話となるが、UTMB準備、チーム100マイルの練習や大会日程以外の週末は全てMC2試走の予定を入れた。
「なぜ丹沢なのか?」
先ずはコースが決まらないと何も決まらない。プロジェクト内では丹沢じゃなくてアクセスの良い高尾や奥多摩でも良いのではないか?という熱い議論をする場面もあったが、南高尾や奥多摩ではトレイルレースをするコースはとれるが、マウンテンスキルを問われるマウンテンランニングレースとしてのコース設定が難しかった。また、ハイカーとの接触をなるべく減らす為に、人気(ひとけ)の無いエリアを選ばざるを得ないのだが、奥多摩や高尾や表丹沢では紅葉の季節には登山道に行列が出来るほどなので除外した。
そのため、東丹沢エリアに目を向けると、このエリアはヒルの群生地帯ということもあり人気(にんき)がないので交通の便も開拓されておらず、自然の姿が残っているバリエーションルートや沢が豊富にあることがわかっていた。そして11月は寒くてヒルは出ないのでその時期なら選手やクルーがヒルの被害に合う可能性が低い。この山域を使わない手はないと思い、コースの山域をこのエリアに絞り込んでいった。

試走風景:コース試走クル―は何人もヒルの餌食となった。ヒルの吸引力はもの凄く強くて、手で引っ張っても簡単に取れないのでヒル撃退スプレーは必須だ。
「関東の山にしかに無いものとは?」
あくまで個人的な意見だが、ぶちゃけ関東の山は普通すぎてどうやっても地方の山には景色やワイルドさで負ける。しかし、地方の山になくて関東の山にあるのは「富士山」だ。丹沢の稜線から見える富士山はいわば「関東のキラーコンテンツ」(笑)になることは間違いなかった。ただし富士山は天候に左右されるので見えればラッキーで、富士山が見えない場合でも十分楽しめるコース作りを目指した。

試走風景:10回以上足を運んで富士山が見えたのは3回ほどだった。この時は雨なのに珍しく富士山が見えた。
「改めてマウンテンサーカスの基本思想に戻る」
せっかく地方で草レースに参加するなら、その土地の人にアテンドしてもらわないと行けないとっておきの場所に行きたいものだ。MC1でもそれが嬉しく、楽しかった。裏丹沢には早戸川の渓流の奥地に日本滝百選の幻の滝と呼ばれている「早戸大滝」があり、何度も渡渉を余儀なくされるので行くのが大変なのが幻の滝と言われる所以だが、関東以外の人なら尚更アテンドしてもらわないと行こうとも思わない場所と言えるだろう。また、早戸大滝に至る約2kmの沢は沢ヤにとっては簡単すぎる沢(沢装備無しで進めてしまう)なので、この「とっておきの場所感たっぷりの滝」と「ハードコア過ぎずイージー過ぎ無い」この沢セクションがマウンテンサーカスにピッタリだと思い、ここをコースに組み込み、富士山が見える稜線とを繋いだことで一気にMC2のコース具体案がまとまっていった。

試走風景:このように広い沢なので川の横を通って進むことができるのが、沢ヤには物足りない点と言える。

試走風景:落差50mの早戸大滝。危険個所もあるので必ず山に慣れた人と行きましょう。

試走風景:今回のコースでは通らなかった雷滝。当初はこちらを通る予定であった。個人的には雷滝の方が好きだ。まだまだコース開拓の余地はある。
こうして、沢あり、滝あり、バリエーションルートあり、急登あり、ブナ林あり、富士山が見える極上トレイルありと、距離20kmの中に山の要素をギュッと濃縮した良い意味で「関東らしくない」ハードなマウンテンランニングコースが完成した。距離は20kmだが、累積標高は約1900mもある。体感的には30km~35kmくらいに感じるハードなコースとなった。

試走風景:丹沢のバリエーションルートには優しい雰囲気のブナ林が多く存在している。
そして出来るだけクルーにコースを試走してもらいたくて、9月、10月はほぼ毎週のように試走会を企画してクルーをコース試走に連れて行った。いろいろなスキルの違いがある人が参加していたので、コースタイムや関門時間決めの参考にもなったが、選手と同じコースをスタッフも走っていることで「大会の一体感を上げる」ことが狙いだった。これはMC1から学んだ重要なポイントだ。そして、クルーを試走に連れて行くとみんなの反応が良く、コースレイアウトに手応えを感じていたが、11月で水温が10℃にも満たない冷たい水の沢に選手やスタッフを渡渉させるか?については大会当日のスタート直前まで葛藤があった。面白さとリスクは常に表裏一体だ。

試走風景:透き通った沢。夏は気持ち良いのだが、大会当日は晩秋。水温は10℃を下回る。

試走風景:想定しいたコースが崩落していて、コース変更を余儀なくされる場面も。
「安全対策」
ここからがようやく今回の核心の話と言える。選手のblogなどからは、単にハードなコースを何の対策もなくゲリラ的に楽しんでいるだけの大会と受け止められなくもないのでその点について触れたい。
大会の基本思想は「オウンリスク」とはいえ、何の対策もせずオウンリスクと言い放つのは違うと思っていた。MC1では現役の看護士でもあるMRHCのメンバーを中心にコースクルーへファーストエイドの講習をした上で運営されていた。MC2ではチーム内にいる現役医師によって全スタッフ向けに安全講習をおこなった。
「救助のプロが来るまでに素人の我々に出来る事は何か?」
を知った上でコースクルーがファーストエイドキットを持って大会当日に山に入っていたのだ。
「怪我よりも恐れていた事」
怪我は山のアクティビティだから当然あるとはいえ、たとえ骨折しても人は直ぐに死ぬことは無いが、「低体温症」になったら人は簡単に死ねる。まして10℃も満たない気温で沢を通るなら怪我よりも低体温症の対策をすべきと医師からのアドバイスを受けて、沢セクションのクルーの強化と、大会の必須装備に着替えや替え靴下を加える対策をおこなった。もし沢で滑って全身が濡れても、その場で即着替えれば低体温症の危険性がかなり下がるからだ。そして、ROD!!には沢ヤが4,5人いて、特に水深の深い渡渉ポイントにその沢ヤを配置し、基本は放置だが選手の状態を見て必要であればロープを渡し、万が一選手が流されても救助できる体制を組むことができた。さらに沢セクションにマーシャルクルー並走させて全部で大小9か所ある渡渉ポイントの監視をおこなった。

試走風景:雨天時の調査の為、敢えて雨の日に試走をおこなった。天気予報の降水量をチェックしておき、雨天決行する際の判断材料とした。自然のストックを利用する渡渉もスキルの一つだ。
次にクライミングセクションの対策だったが、ここは約50m程の高さで斜度70%程の急セクションで、ここはROD!!にはボルダラーがいるので彼らを監視員として配置した。

試走風景:斜度70°の直登セクション。ロープを使うか?岩場を登るか?その人のマウンテンスキルによって選択ができる。

試走風景:女子でも容赦なく厳しい直登ルートで藪こぎする場面も。
そして、大会の当日はゴールに医師と看護士に待機してもらっていた。
また、最悪ヘリを呼ぶ可能性もあるので選手とスタッフ全員にイベント保険をかけた。チーム内に保険会社に勤務するものがいるので、安いながらしっかりとした保険プランをカスタマイズできたのは助かった。
医師、看護師、医学療法士、沢ヤ、ボルダラー、保険屋と、何かしらその筋に長けたメンバーがROD!!とTOBA両チームにいて人材的にとても恵まれていたことで、アマチュアができる限りの安全対策対策を構築することができた。
このように両チーム内にとても頼もしいメンバーがいたからこそ勇気をもって沢の渡渉と、斜度のある危険なクライミングセクションをコースに組み込む決断が出来た。彼ら無しでは今回のコース設定は不可能だっただろう。
「交通の問題」
安全対策の次に頭を悩ませる問題であったのが、当日の大会スタート地点に自家用車を使って50人の選手を送迎することだった。バスを借りれば一発解決なのだが、低予算の草レースだけにバスをチャーターする予算は無い。そこで選手とクルーの自家用車を使って選手をスタート地点へ送迎することにしたのだが、運転手も選手だったり、駐車場が少なかったり、複雑な選手送迎のプログラムを組んだ。また、この山域は携帯電話が通じないので迷ったら終わりだ。これは鳥羽ちゃんの大倉さんが一手に引き受けていたのだが、複雑パズルのようなシフトだったにも関わらず、見事に定刻通りに最終ウェーブの選手がゴールラインに並んでいるのを見た時には本当に感動した。まるで電車の時刻表を作る「スジ屋」のようだった。
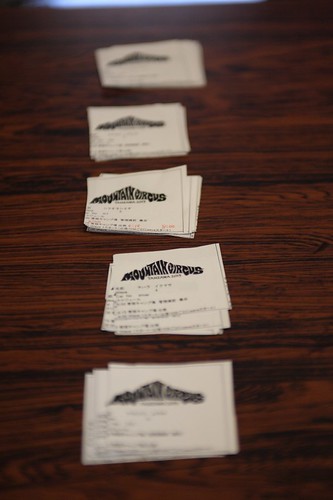
乗車整理券。レース当日は整理券の番号の車に乗るように準備していた。
「webサイト」
上記で書いたが事前にイベント保険に入ったり、ファストエイドの医療品、スタッフ用キャップ、参加賞品の用意や前夜祭の用意などがあった為、資金確保の為に公式ページから事前入金にしてもらい、併せてエントリーの際にイベント保険加入に必要な選手の情報や自家用車の有無を記入してエントリーをしてもらうことにした。これもチーム内のwebデザイナーとwebエンジニアによって自前のシステムを組んでもらった。
その他、会場/前夜祭班、賞品班(参加賞品を自分達で作った)、タイム計測班、エイド班が事前準備をしていたが、これらはこの次の大会編で併せて紹介したい。
こうして5か月の準備期間を経て大会当日を迎える事となった。
⇒「草レースやろうぜ!」MOUNTAIN CIRCUS 2 TANZAWA(その3)へ


![Coordination
[MMA Cool Pile 2tone Big Tee ]
"Blue_White"
XS: out of stock
S: out of stock
M: in stock
L: out of stock
XL: out of stock
[MMA CORDURA®︎ JOURNEY 8pocket Shorts ]
"Gray"
XS: in stock
S: in stock
M: out of stock
L: in stock
XL: out of stock
※SNSのコメントやメッセージでのご質問には対応しておりません。商品に関するご質問はお手数をおかけいたしますが、公式サイトもしくはWEBストアからお願いいたします。
#mountainmartialarts
#マウンテンマーシャルアーツ
#TMRC
#tokyomountainrunningcompany
#norunningnolife
#MMAstagram
#MMAmaniacs
#running
#trailrunning
#trekking
#runningwear
#ランニング
#トレイルランニング
#トレッキング
#登山
#ランニングウェア](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/364945657_1445380922928177_1843578066858236543_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=kqjWcyF3W2oAX9nPKE4&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&oh=00_AfDJLG4YsIuyzDPMhDHOvpc4GwmdNxVsiImqNO_mTyhtug&oe=64D3DE52)
![Coordination
[MMA Border Patchwork Tee]
"Turquoise_Navy"
XS: out of stock
S: in stock
M: in stock
L: in stock
XL: out of stock
[MMA Big Dot 3pocket Racing Run Pants]
coming soon
※SNSのコメントやメッセージでのご質問には対応しておりません。商品に関するご質問はお手数をおかけいたしますが、公式サイトもしくはWEBストアからお願いいたします。
#mountainmartialarts
#マウンテンマーシャルアーツ
#TMRC
#tokyomountainrunningcompany
#norunningnolife
#MMAstagram
#MMAmaniacs
#running
#trailrunning
#trekking
#runningwear
#ランニング
#トレイルランニング
#トレッキング
#登山
#ランニングウェア](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/364354284_307204998451062_5393607903943517677_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=6XJMU1dTRgAAX-OfQ5z&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&oh=00_AfDOyjZRKokDSuvuO01GbyQT7HsHwiVQNrpY05tK_0eeNg&oe=64D3433A)
![[TOKYO MOUNTAIN RUNNING COMPANY : RELEASE INFORMATION]
いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。商品発売のお知らせになります。
https://tmrc.tokyo
発売日時: 2023年8月2日(水)22:00
MMA Border Side Mesh Tee (TMRC exclusive)
MMA Border Patchwork Tee
MMA Cool Pile 2tone Big Tee
MMA Cool Pile Short Pants
MMA CORDURA®︎ JOURNEY 8pocket Shorts
※ご購入の前に、必ず「ご利用上の注意点」をご覧ください。送り先ご住所とメールアドレス記載漏れやミスが増えています。商品が届かない場合もございますので、充分ご注意ください。
https://tmrc.tokyo/pages/rule
ボーダー
接触冷感パイル
COOLMAX
機能を備えた夏らしいデザインのプロダクトが揃いました。暑い夏の日を、機能の力で楽しく快適に過ごしましょう。
※SNSのコメントやメッセージでのご質問には対応しておりません。商品に関するご質問はお手数をおかけいたしますが、公式サイトもしくはWEBストアからお願いいたします。
#mountainmartialarts
#マウンテンマーシャルアーツ
#TMRC
#tokyomountainrunningcompany
#norunningnolife
#MMAstagram
#MMAmaniacs
#running
#trailrunning
#trekking
#runningwear
#ランニング
#トレイルランニング
#トレッキング
#登山
#ランニングウェア](https://scontent-nrt1-2.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/364959005_1664708180702332_1127661303872672669_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=EV_BeV6Xg-YAX_cY-xy&_nc_ht=scontent-nrt1-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&oh=00_AfCFQ9kMVDJ-ub3zQLzNzavK-IjGyyef50FRGnqRPUnnOA&oe=64D2C520)




